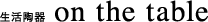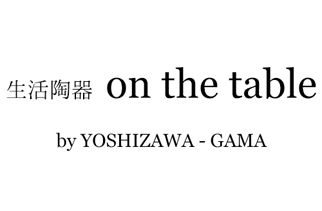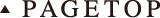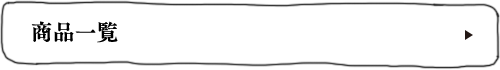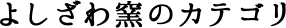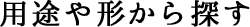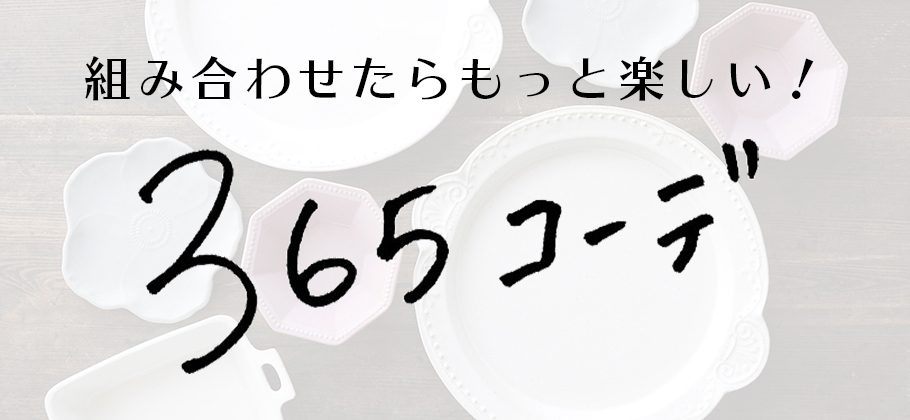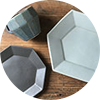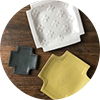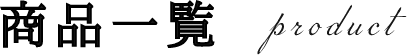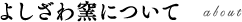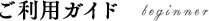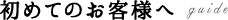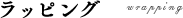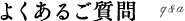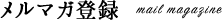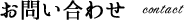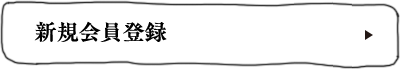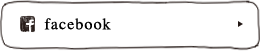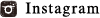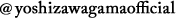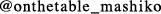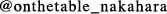大人の自由研究的な気分で、先月から少しずつ進めてみていたフローラルマグの金継ぎ。
今回はその報告編です!

ふちの部分がぱきっと割れてしまった、お気に入りのマグ。
これまでは合成樹脂を使う簡易金継ぎしかやったことがなく、本漆の金継ぎにも挑戦してみたいな…とかねがね思っていたので、ついにやってみることにしました!というのが前回のお話。
→【前回の読み物はこちら】

教室に行く、という方法もあると思いますが、ひとまず自分のペースでできるときに進めてみたかったので、材料一式が揃ったキジマツさんの金継ぎセットを購入。同梱されているマニュアルを見ながら探り探り進めていきました。
☆ここからは、あくまで私がやってみた感想を・・・必要なものや工程などは教室で教えてもらうか、キジマツさんのようなセットで揃えてマニュアルなどを見ながら進めるのがよいかと思います。

一番はじめにこんな工程があるんだ!と思ったのは、割れた部分の「面取り」をすること(大根の煮物的なアレです)。
割れた角の部分を削ることで、漆が入り込みやすく、溝が太くなるので線もしっかり引けるようになるとのこと。
これまで簡易金継ぎをやったときは破片同士をくっつけたあと、うっすら見えるか見えないか…くらいのヒビを上からなぞっていた(=ものによってはかなり細い線で仕上げていた)のですが、たしかによく見る金継ぎされた器は結構線がしっかりしているなあと。こんなに序盤からそのように仕上がる理由があったんだ…と思いました。
 (はじめに接着したところ。ここから埋めて金を蒔いていくので、まだまだこれから!という感じですね)
(はじめに接着したところ。ここから埋めて金を蒔いていくので、まだまだこれから!という感じですね)

なにげに苦戦したのが、錆漆を塗る前にマステを貼る工程。(きっと器用な人はなんでもないと思うのですが・・・笑)
溝にしっかり錆漆を埋め込むために、塗る必要のない部分をマスキングしておく、というものなのですが、特に小さい欠片のほうは、割れに沿って貼っていくのが難しかった…。複雑な割れ方をしたときはどんなふうに貼るのがいいんだろう。。

乾いてからマステをはがすと、こんな感じに!
なんとか溝は埋まっていて安心しましたが、不要な部分は削らないといけないので、できるだけギリギリのところにマステを貼れるとよさそう…これはだいぶまだまだ線が太かったので、ここからガリガリ削っていきました。

太い部分を削ったあとは、やすりで整えて漆の中塗りへ…漆は何回かに分けて薄く塗っていくのですが、割れたところの先もヒビが入っていたので、少し長めに伸ばしてみました。いよいよこの形で金を蒔くんだ!とイメージできてわくわくします。

そして一番のお楽しみ、金を蒔く工程!
簡易金継ぎでは真鍮粉を合成樹脂に混ぜて塗っていたので、「蒔く」という工程自体初体験。
素早く綿を動かして金をのせていくのはコツがいるな…と思いましたが、ここまでの工程で1か月ほど経っていたので、ようやく完成の姿が見えた!というのは素直に嬉しかったです。

その後、仕上げの工程まで終えて、先日ようやく完成したところ。
こまかいことをいえば、ここが荒かったな…など、気になる部分は多々あるのですが、ひとまずまたマグカップとして使えるようになってくれて安心しています。
簡易金継ぎに比べると、思い立ったときにすぐ直せる!というわけではないですが、ひとつひとつの工程自体はそこまで時間がかかるわけではないので、少しずつ進めるのを楽しみにする…というのは、私は結構自分に合っているなと思いました。
ただ、今回のマグはマットなうつわで、意図しない部分に漆が入り込んでしまうのにちょっと苦戦しました。最初にやってみるなら、つるっとしたうつわがよいのかも。(ほかにも要因があるかもしれないので、違っていたらすみません…)
質感や用途など、直したいものによって本漆と簡易と使い分けられるとよいのかな、と思うので、どちらの方法も使いこなせるように、また器が割れてしまうことがあったら、前向きにチャレンジしてみたいです!
table__or_
→→《よしざわ窯のある暮らしTOP》